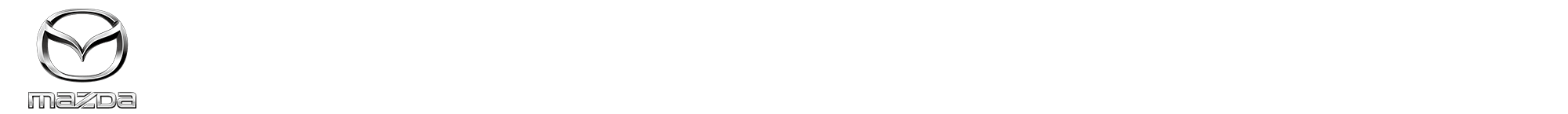手話は日本語や英語などと同じ言語のひとつ ~多様性への対応~
明日、9月23日は「手話言語の国際デー」です。国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを目的に制定されました。
マツダは、従業員の多様性を尊重すると同時に従業員一人ひとりが個性を発揮しながら、力を合わせて会社や社会に貢献する企業風土の醸成を目指しています。
その活動の一環として、障害のある人を安定的、継続的に採用。各々がその能力を最大限に発揮できるよう、相談窓口「フィジカルチャレンジサポートデスク」を設置し、就労環境の整備、ならびに、さまざまな相談事項に対応しています。
今回は、フィジカルチャレンジサポートデスクの活動および、メンバーとして手話通訳を担う社員の活動についてご紹介します。
 フィジカルチャレンジサポートデスク メンバー
フィジカルチャレンジサポートデスク メンバー
左から、勝丸孝子、大竹智也、西尾香月
フィジカルチャレンジサポートデスクとは
大竹:
フィジカルチャレンジサポートデスクでは、手話通訳士の派遣、さまざまな障害を持つ社員の環境確認・整備や、職場へのサポートを行っています。
私たちの仕事は、障がい者の方向けと思われがちですが、それだけではありません。入口のドアを引き戸に変える、段差を解消する、席までの動線を確保する、などの職場環境整備と共に、着任先の職場にいる方々と相談、対話をしています。
配慮が不足しているところもあれば、逆に過度に配慮しすぎて受け手がプレッシャーになりそうなところもあります。適切な環境整備ができるよう、相互理解につながる場づくり、マインドセットが重要だと考えています。

一人ひとり状況は異なり、それぞれのケースにあわせて環境を整備しています。
聴覚に障害を持つ社員が各部署に着任後、本人とも話し合いを行って不足な箇所があれば追加で対応しています。
社内手話通訳士の仕事とは
マツダの障がい者在籍数は現時点約400名。そのうち最も多いのが、聴覚障害。
こうした社員たちと、関係する社員たちへのコミュニケーションを充実させるため、マツダでは2名の手話通訳士が正社員として在籍しています。
社内手話通訳士として活躍する西尾と勝丸に話を聞きました。
― 社内での手話通訳というのはどのようなものを対応しているのでしょうか
勝丸:
各部署のニーズに応じて対応をしています。
重要な経営メッセージを伝える必要がある場合はもちろん、会議での通訳、上司と部下の1対1での会議など、部門からのニーズや社員の方からの相談に応じて、幅広い業務をカバーしています。
 オンライン会議でも対応します
オンライン会議でも対応します
工場では、研修や資格を取るための勉強会、実技練習など、安全管理や技能向上のための通訳が多く、開発部門では、会議での通訳が中心ですかね。
― マツダ社内で活動していて、苦労した点、課題と思われる点はありますか
西尾:
マツダで手話通訳を始めた頃、自動車の知識が十分に無かったことです。例えば、内燃機関係の用語「ウォータージャケット」が何か分からず、「水の上着」と手話で表現して、笑われたことがあります(笑)。
「魂動デザイン」といったマツダ用語や、MMVO(Mazda de Mexico Vehicle Operation)などのマツダ略称にも苦労しましたね。

手話自体の理解がもっと促進されるといいと思います。手話は日本語の単語を動作で置き換えたものではありません。独自の表現や文法を持つ、ひとつの言語です。
手話通訳は「通訳」であるとの認識が一般的に薄く、手や腕を動かして言語を「変換」しているだけと思われがちです。でも実は音声言語の通訳者とやっていることは全く同じ。
異なる言語をもつ複数名の間にたち、コミュニケーションを円滑にします。単語を単に変換して伝えるのでなく、話者の意図を正確に伝えることが通訳なのです。
勝丸:
もうひとつ、勘違いされやすいのは、「聴覚障がい者=手話ができる」と思われがちなところですかね。手話を習得していない社員もいます。
手話が第一言語で、第二言語が日本語という方もいます。その場合、流暢に日本語で筆談できるとは限りません。
職場の方が、この状況を理解するだけでもコミュニケーションは改善されます。やはり相互理解が大事ですね。

新入社員の時から、意識できるように
― 理解を拡げるために、他になにかされていることはありますか
大竹:
社内の方々の相互理解はとても大事だと考えています。
そこでマツダでは2017年から、新入社員研修プログラムの中に「聞こえない人とのコミュニケーション講座」を120分枠で実施しています。
繰り返し実施していけば、社内の理解者は確実に増えていきます。
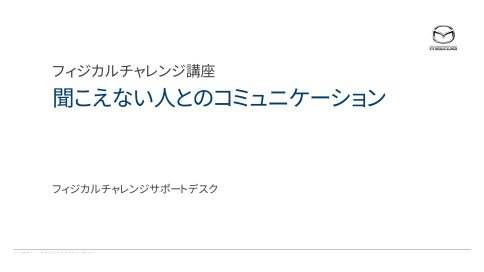 |
 |
| 2023年の様子 複数の部屋に同時中継する | |
勝丸:
手話はすぐに覚えられるものではないので、この講座ではほとんど触れません。
聴覚障がい者の中には、手話が出来ない人もいれば、日本語が苦手な人もいます。聴覚障がい者とひと言で言っても十人十色。コミュニケーションをとる時に大事なポイントを体験学習など交えながらお伝えしています。
 |
 |
|
お互いに喋らずにコミュニケーション体験 |
|
手話ができなくても「アイコンタクト」をしながら、「筆談」や「口話」を相手に合わせて組み合わせ、内容を曖昧にせずにしっかりとお互いに確認をとることが大事です。
少しずつ理解の輪を拡げていく
西尾:
毎年、聾(ろう)学校出身の新入社員が入社します。彼らにとっては、全く異なる環境に身を置くので不安が大きい。
「聞こえない人へのコミュニケーション講座」を聞くことで、同期達の理解が進んだのでしょう。行動ががらりとかわり、積極的にコミュニケーションをとってくれるようになったそうです。緊張が解けて、不安が和らいだと、すごく喜んでくれました。

職場によっては、先輩社員達からの講話があるのですが、その中に聴覚障がい者の社員が登壇したり、普段の会議の後に「私の意図をすべて伝えてくれてありがとう」と感謝の声をもらうなど。
少しずつかもしれませんが、確実に理解の輪が拡がっていると思います。障害の有無に関わらず、一人ひとりの社員が力を発揮できる職場づくりをしていきたいですね。
いかがでしたでしょうか。MAZDA BLOGではこれからも、マツダの各領域で働く社員を紹介していきます。
最後に手話に関するクイズです。
この動画はマツダ内で使用している単語を表現しています。
▼何を意味しているか、お考えください。
▼回答はこちら