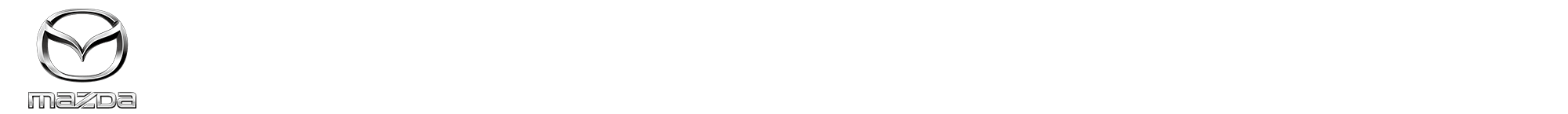『匠塗 TAKUMINURI』を支える“研ぎ”の技 ~ソウルレッドクリスタルメタリックとマシーングレープレミアムメタリック
『匠塗 TAKUMINURI』と名付けられた2つの色、ソウルレッドクリスタルメタリックとマシーングレープレミアムメタリック。この特別な2色は、従来の技術では生み出せないさまざまな特性の上に成り立っています。
量産化するには、塗装の現場も今までの殻を破る必要があり、その努力は一見目立たない下地づくりの工程にも及びました。美しい下地づくりに欠かせない「研ぎ」のプロセス一つに込められた、技術者たちの情熱をご紹介します。

<目次>
・「匠塗 TAKUMINURI」のカラーとしての特殊性
・従来の「研ぎ」が使えない!唯一無二の色を世に出すために
・色ムラがなくなるまで重ねた練習
・美しく研ぐための工夫は、すべての工程の環境づくりにまで及ぶ
・生産技術から工場スタッフまで、共通する問題意識が生んだ美しい色
『匠塗 TAKUMINURI』のカラーとしての特殊性
『匠塗 TAKUMINURI』の2色は、魂動デザインが追及している光の移ろいを表現するために、発色を担う発色層と光の反射を担う反射層を2層重ねた特別な塗装をしている。特に、光を正確に反射させる役割をもつ反射層では、ミクロン単位の小さなアルミフレークを水平にならべなければならない。
そのために反射層の厚みを通常塗装の半部以下にまで極薄にすることでアルミフレークを水平にならべている。発色層と反射層の相乗効果が、ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリックの、他のメタリックカラーとは異なる艶やかさや深みを生んでいる。

しかし、塗膜を薄くするということは、求められる条件が厳しくなるということでもある。従来の塗装なら許容されるような多少の凹凸や厚みの差がゆるされない。
塗膜を薄くするには塗料にも工夫が必要であり、塗料成分の粒子を細かくすることに加えて、光輝材のアルミフレーク一つひとつの厚みと大きさを均一にする必要もある。
さらに、よりシビアに問われるのが塗装の下地である電着面の状態だ。
「反射層が薄いぶん、下地に凹凸があると発色への影響が大きい。下地の研ぎの精度が問われるのです」と製造部門係長の河内誠二は語る。

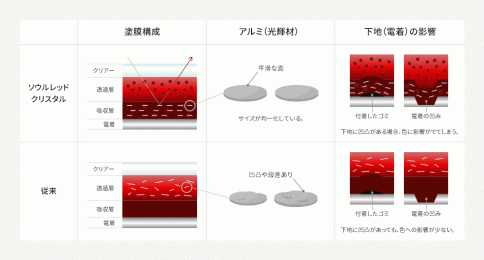
『匠塗』塗装と従来の塗装の比較。光輝材や電着面の状態がよくないと『匠塗』は成立しない。
従来の「研ぎ」が使えない!唯一無二の色を世に出すために
そもそも「研ぎ」とは何か?
クルマの塗装は、車体工場で鉄板部品を溶接で組み立てた後、塗料が入った巨大な槽の中に、ボディを丸ごと浸漬させて、外からでは塗りにくいパーツの内部まで塗膜を形成するところから始まる。
この最初の工程が電着塗装だ。ところがこの工程ではどうしても、処理中に小さなゴミが混入したり、表面にごく小さな異物が付着したりすることがある。そうしたゴミや異物を人の目で見つけ出し、特別に開発された専用の研磨紙を用いて表面を平滑にするのが「研ぎ」の工程だ。


「目的は電着面の凹凸をなくすこと。そういう意味では研ぎ方は、従来は最も手早くできる一方研ぎ(前後方向にこする方法)で研いでいました。しかし『匠塗 TAKUMINURI』の場合、この方法で研ぐと、塗膜が乾燥したあとに、跡が残って見えてしまうことが分かりました。新しい塗装に合わせて研ぎ方にもこれまでとは異なる工夫が必要でした」

(写真:下地の研ぎ跡が塗装の上からでも分かるため、研ぎ方の違いで模様を描き出すこともできる。
参考作品として作った桜模様のボンネットはこうして作られた。)
河内が思い出すのは、ソウルレッドクリスタルメタリックが量産に入る前、生産準備の段階でトライアル塗装に立ち会った日のこと。その深い輝きは一瞬で河内を魅了する。「この色をどうにかして世に送り出したい」――しかし塗装工場で長く経験を積み重ねてきた目で見れば、その難しさもすぐに想像がつく。量産へのチャレンジは、「今までの殻を破る必要がある」という覚悟とともに始まった。
色ムラがなくなるまで何度も重ねた練習と検討
従来の一方研ぎが使えないとなると、何か新しい研ぎ方を探し出さなければならない。さまざまな試行錯誤の結果、円を描くように研ぐ「回転研ぎ」であれば、塗装乾燥後に跡が残らないことが分かった。
しかし実際に現場でやってみると、回転研ぎは圧のかけ方が難しく、一方研ぎには十分熟練したスタッフであっても研ぎムラが出る。最適な圧のかけ方を、どう標準化していくのか?
製造部門職長代行の池田敦史が、この問題を解決するため、「感圧紙(圧力がかかると発色する特殊なフィルム)」を使った方法を提案した。
「感圧紙とは、もともとは配管工事の際、余分な圧力がかかっている個所がないかどうかをチェックするためのツールで、圧力がかかった部分に色がついて見えるようになっています。これを研磨紙でこすると、力のムラが色ムラになって目に見えるんですね。そこで研ぎのスタッフには、これを使って色ムラが出なくなるまで練習を重ねてもらうことにしました」


感圧紙を使った回転研ぎの練習だけで約1週間。
それから実際のパーツを使って訓練する。
「平面で練習しても、実際に研ぐのは曲面の車体。今の魂動デザインには、複雑な曲面も多く使われていますから」と池田。ひと通り研ぎをマスターしたら、その上の塗装を施して不具合がないことを確かめて初めてOKが出る。こうして実際にスタッフがラインに入れるようになるまでには、約1カ月の時間を要した。
研磨紙についても検討をする必要があった。
従来の研磨紙は粒子の大きさにばらつきがあり、『匠塗』に使うとキズが入ってしまう。
かといって粒子の細かい研磨紙を使えばキズは入りにくいが、研ぎ作業の時間が長くなってしまう。
最適な研磨紙を見つけ出すまでには、研磨紙メーカーと工場、さらに生産技術も加わった3者が何度も検討を重ねた。
美しく研ぐための工夫は、すべての工程の環境づくりにまで及ぶ
しかし、どんなに研ぎの技術を磨き、ツールの工夫をしても、一方研ぎよりは時間がかかってしまうのが回転研ぎ。スピードアップも大きな課題だった。「何しろ、製造ラインでは50秒に1台のペースで車体が流れてくるわけですから!しかも、1つの車体につきだいたい20カ所程度は研がなければなりません。のんびり研いでいては間に合わないのです」

スピードアップを図るために、研ぎの技術だけでなく、その手前の工程や、作業工程環境全体についても見直しを行った。
たとえば前工程である電着の品質アップ。そもそも電着の段階でゴミや異物が少なければ、研ぎの負担は軽くなるからだ。研ぎのブース内にも工夫を施した。作業には拭き取り材や研磨紙などさまざまなツールを使うが、これを取りに行ったり戻ったりする時間も惜しい。「1秒でも2秒でも、ゴミの検出と研ぎに当てたい」という河内の思いから、スタッフの移動距離が少しでも短くて済むよう、車体が動くとツールの入ったケースが自動でついてくる「同期台車」を開発、工場スタッフ自ら手作りして導入した。
さらには、電着面に触れる際に身につけるゴミ検出用手袋の材質まで見直した。ゴミや異物は目視のほか、手で触れて見つけ出すが、それをいち早く見つけられるよう、さまざまな材質の手袋を着け、実際に何度も触って確かめたという。
「塗装品質の造りこみは、『きれいなボデー』『きれいな塗料』『きれいな乾燥炉』『きれいなブース』、の「4つのきれい」 を大切にすることで美しい色を世に送り出せています。そのために工場も生産技術も一丸となって取り組んでいました」
生産技術から工場スタッフまで、共通する問題意識が生んだ美しい色
「この色はマツダにしか出せない」と河内は言う。
その言葉には、塗料の美しさだけではなく、それを量産で実現するために取り組んできたことへの確固たる自信がこもっていた。
「新しい塗装を量産に落とし込むのは本当に難しい。でもこの工場には、今までの殻を破る必要が出てきたとき、それをネガティブに捉えるのではなく、前向きに考える風土があります。生産技術の側も、量産準備が終わったらあとは工場任せというのではなく、僕らのアイデアを反映した材料を常に提供してくれる。
『美しい面を作りたい』という思いは同じであり、そのために何ができるのかという問題意識が全員にある。そのことが、この美しい色を生み出しているのです」

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
公式ブログでは、モノづくりを支える技術者の姿をご紹介していますので、こちらもご覧ください。
■クルマのボディーづくりを陰から支える「ロボットインストラクター」
https://blog.mazda.com/archive/20200630_01.html
■【世界一を目指す職人たち】塗装シーラーの「一筆書き」に迫ります!
https://blog.mazda.com/archive/20171107_02.html